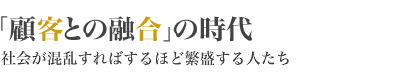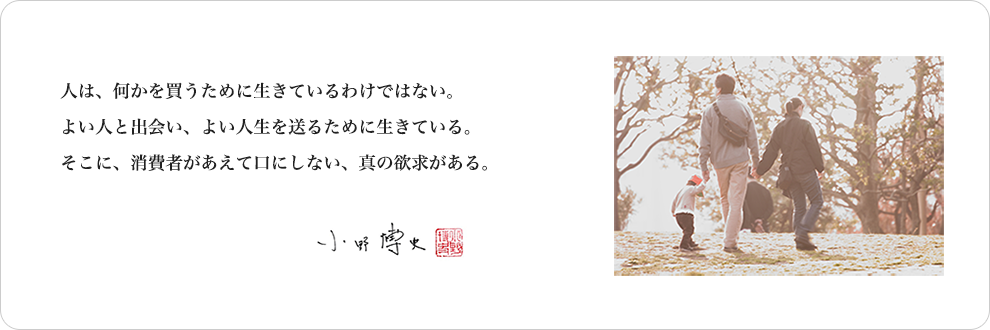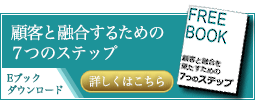ビジネスお役立ち知識
人事異動の基本に立ち返ることで見えてくるもの
『経営の父』と呼ばれた経営学者、ピーター・ドラッカー氏。経営に関する多くの名著を残した氏が提唱した経営革新手法の一つに『ナレッジマネジメント』があります。個人の持つ知識や情報を組織全体で共有し、有効活用することで業績を上げようという経営手法のことで、この場合の知識や情報とは、物理的なものだけでなく、個人の経験則やノウハウまでを含めて広義に解釈したものを指します。(IT用語辞典 e-Wordsより)
ナレッジマネジメントが注目されてから約10年。日本でも多くの企業が導入したようですが、言葉だけが先行して思うような効果につながっていない、という話も耳にします。
ところで、個人の能力を最大限生かした組織作りがナレッジマネジメントの基本だとすれば、日本の企業は昔から、似たようなことをしてきました。それが『人事異動』です。
企業では少なくとも数年のうちに1回、多いところでは1年に数回。定期的に、あるいは必要に応じて人事異動を行います。その目的は適材適所だけでなく、会社全体を把握するための経験であり、得意・不得意を見極めながら専門分野を開拓する自己鍛錬であり、新しく出会った同士が知識や情報を交換することで職場に活気を与えるカンフル剤でもあります。優れたチームワークも、長年同じメンバーが顔を突き合わせていたら、そのうちマンネリの馴れ合いが生じて鈍化します。
人事異動は社員の専門性を高めることに逆行する、という意見もありますが、経営者であれば『かわいい子には旅をさせろ』の精神も必要なのでしょう。
人は、人から受ける刺激に最も触発されるものです。その意味でも人事異動で人材を入れ替えることは、会社全体の士気を高め、生産性の向上にもつながるでしょう。当たり前に行われている人事異動ですが、一度基本に立ち返ってみることで見えてくるものがあるように思います。