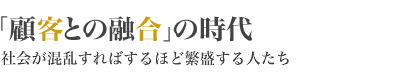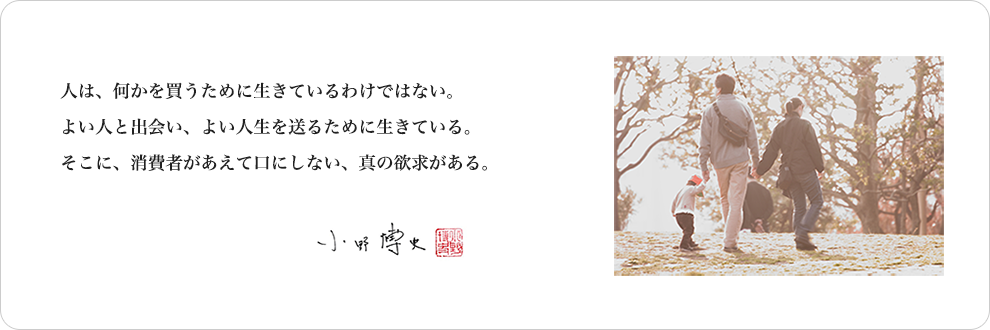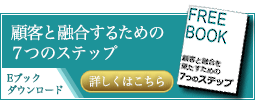ビジネスお役立ち知識
“こどもロジック”に学ぶ!売れる商品の発想法
子どもの頃は空に浮かぶ雲を見て、「あれはお船」「こっちは怪獣が戦ってる」とすぐに何かをイメージできたものです。大人になると、雲を見て瞬時に何かを連想したりストーリーを展開させたりする発想の柔軟性が失われてしまいます。子どもの突拍子もない発想力を「こどもロジック」と名付け、新しいモノづくりの考え方にしようと提案しているのが、(株)ワコールアートセンターチーフプランナーの松田朋春(ともはる)氏です。ちなみに「ロジック」とは「論法、理論」という意味です。
■あらゆるものを“おもちゃ”として捉える
松田氏が最初に考えたのは「トイロジック」という言葉だったそうです。着目したのはおもちゃメーカーの考え方。一般的なモノづくりが“役に立つ”とか“価格競争”を主眼にしているのに対し、おもちゃメーカーは“面白さ”だけを追及しているところがあると分析し、あらゆる物事を“おもちゃ”として捉えたらどうかと考えました。従来の製品をおもちゃとして考え直したとき、今までできなかったもの、なかったものができるかもしれない――。その背景として着想したのが「こどもロジック」だったそうです。子どもの発想のもとは「なんとなく」。なんとなく似ている、なんとなく分かる……。大人には理解できなくても、子どもの目では「なんとなく」でいろいろな物事がつながっていき、何かを連想していきます。「子どもの頃のことを思い出すとエモーショナルだった」と言う松田氏は、モノづくりに子どもの発想(こどもロジック)を取り入れる、つまり人の情動を動かす(エモーショナル)ことでヒット商品が生まれると考えるそうです。
(参考:MIZUHO広報誌「Meme(ミーム)No.10」シリーズ鼎談・21世紀「知」の集団像「新しいモノづくりのパラダイムは“こどもロジック”」http://www.mizuho-ir.co.jp/meme/200407/teidan.html)
大人になると「なんとなく」感じたことはなんとなく忘れていきます。けれど、なんとなく犬の気持ちが分かる気がするので「バウリンガル」が大ヒットしたのでしょう。アイデアは“生み出す”ではなく“浮かぶ”と言います。一生懸命考えるのではなく子どものようになんとなく感じて連想していくと、思わぬことになるかもしれません。