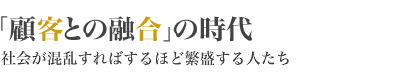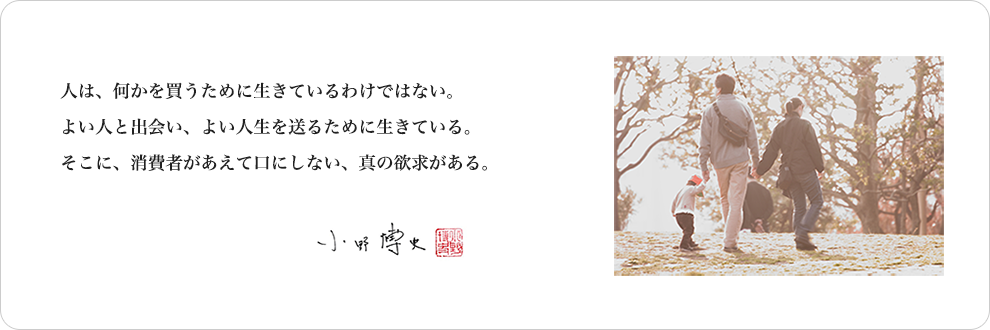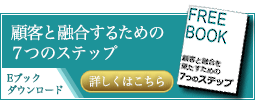ビジネスお役立ち知識
失敗しない、社長と社員のコミュニケーションのとり方。
多くの会社が不況にあえぐ今、業績悪化や雇用体制の修正によって社員の士気が下がりがちです。会社に対する不満が溜まっているだろうと懸念して、社員とのコミュニケーションを密にしようと工夫を重ねている社長もいるようです。しかしその場合、ある程度のルールを設けておかないと逆効果になってしまうことがあります。社長自らが社員と“飲みニケーション”を取り、失敗した一例をご紹介しましょう。
その会社は社員の平均年齢が比較的若く、二代目に就任したばかりの社長も同世代。社長就任前に「同僚」として一緒によく飲んだ社員を誘い、親睦を兼ねた飲み会を開きました。最初こそお互いの立場から遠慮があったものの、もとは飲み仲間。お酒が入るうちに社員は本音を言い始めたそうです。
こんなご時勢ですから会社に対する不満も当然ありました。ところがそのほとんどは、会社の今後をどうしたらいいかという社員なりの考えでした。勤務体制や作業手順、なかには経営理念に触れた意見もあったそうです。「こんなに会社のことを考えてくれているのか」二代目は社員の情熱に胸を打たれました。が、ハタと気づいたのです。自分はもう彼らの同僚ではない、と。
会社のためを思っての意見ですから、社員の言うことにも一理あります。以前なら「そうだよな」と同意したでしょう。しかし、社長の立場で彼らの意見に「イエス」を言うとは、つまり会社として社員に正式な約束をするという意味です。それが酒の席であっても、「社長は了解してくれた」と社員は考えるでしょう。
社長自らが直接社員の声を聞いてしまうと、規模の小さい会社ほど社長自身が辛くなる。かといって風通しの悪い会社では、ますます社員の士気が下がる。それに気づいた二代目は、「社員の話はナンバーツーが聞く」というルールを自分のなかに設けたそうです。ナンバーツーが話を聞き、ナンバーツーから報告を受ける。社長の仕事をひと言で言えば「決断」です。社員の士気が上がるも下がるも社長の決断次第です。会社と社員を守るためにはフラットな立場での決断が求められるでしょう。